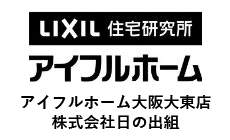お家を建てる前に行われる“地鎮祭(じちんさい)”。
地鎮祭は、お施主様にとって大切な始まりの日です。しかし、詳しく理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。
今回は、地鎮祭の流れや地鎮祭で使用される代表的な道具やその意味についてご紹介します。それぞれの意味を知った上で参加すると、地鎮祭がより心のこもったものとなります。

地鎮祭とは?
地鎮祭とは、お家を建てる前に土地の神様に工事の安全と家族の繁栄を祈願する儀式のことです。
地鎮祭の費用や手配について
地鎮祭の費用は、神主への玉串料4万円~6万円程度が一般的です。地域や神社、宗教によって金額が異なるため事前確認が必要です。
地鎮祭の手配については、私たちアイフルホーム大阪大東店にご依頼いただけます。
ご自身で手配される際は、土地の氏神様を祀る神社へ直接ご依頼ください。氏神神社が分からない場合は、お住まいの都道府県の神社庁に問い合わせると調べてもらえます。手配する際は、神主さんのご都合もあるため、1か月前までに依頼するのがおすすめです。
地鎮祭って必ずやらないとダメ?
地鎮祭はお家を建てる前に行われる儀式ですが、必ず実施しなければならないわけではありません。地鎮祭を行うかどうかは、お施主様自身の意向により決定されます。
ただ、「せっかくだし記念に残したい」「気持ちを引き締めたい」といった理由から、多くの方が地鎮祭を行われています。地鎮祭は、お施主様にとって大切な始まりの日でもあります。家族の気持ちやご都合に合わせて、地鎮祭を行うかどうかを決定することが大切です。
地鎮祭の一般的な流れ
- 修祓の儀(しゅばつのぎ)
参列者やお供え物を清める儀式です。神主さんがお祓いの言葉を奏上し、お祓いします。 - 降神の儀(こうしんのぎ)
土地に鎮まる神様や地域の神様をお迎えする儀式です。 - 献饌(けんせん)
神主さんが祭壇のお神酒と水の蓋を取り、神様にお供え物を捧げます。 - 祝詞奏上(のりとそうじょう)
神主さんが祝詞を奏上し、神様に祈りの詞を捧げます。これから土地をお借りし、家を新築することを神様に奉告する儀式です。 - 四方祓いの儀(しほうばらいのぎ)
敷地の四隅と中央をお神酒・米・塩・白紙で清めます。 - 地鎮の儀(じちんのぎ)
土地を鎮める儀式です。まず、設計者が鎌で草を刈る「刈初め」を行い、お施主様が鍬で盛り砂を起こす「穿初め」を行います。その後、神主さんが鎮め物を納め、最後に施工業者が鋤で砂を均す「土均し」を行います。
刈初め、穿初め、土均しは、それぞれ3回「えい、えい、えい」と声を出しながら行います。 - 玉串奉奠(たまぐしほうてん)
参列者が順番に祭壇の前に立ち、玉串を捧げ工事の安全を祈願します。 - 徹饌(てっせん)
神主さんがお神酒と水の蓋を閉じ、お供え物をお下げします。
地鎮祭で使用される主な道具と意味

忌竹(いみだけ)
祭壇の四方に「忌竹(いみだけ)」と呼ばれる竹を設置し、しめ縄で囲うことで祭壇内を聖域としています。

神饌(しんせん)
神饌(しんせん)とは、神様へのお供え物のことです。一般的には、お米、塩、酒、水、旬のものなどをお供えします。
玉串(たまぐし)
玉串(たまぐし)は、神前に捧げる榊(さかき)のことです。玉串奉奠(たまぐしほうてん)の際に使用され、神様と人間の仲立ちをする意味を持ちます。榊は、古来から神が宿る植物とされており、「神と人の境界にある木」という意味のある神聖なものです。

地鎮の儀(じちんのぎ)に使用される道具について
お施主様と施工者が神様に着工を告げるために、土地をイメージした盛り砂や鎌、鍬、鋤を用意します。地鎮の儀の際には、鎌で草を刈り、鍬で土を掘り起こし、鋤で土地を平らにする所作を行います。この時の「えい、えい、えい」という掛け声には、「栄」という意味も含まれています。
また、地鎮の儀で神主さんが納める鎮め物は、箱や封筒など地域や神社によって異なりますが、中身は人型・盾・矛・小刀・長刀子・鏡・水玉の7つが入っているとされています。土地の神様にお供えすることで、工事の安全やこれから建てるお家の繁栄を願います。
アイフルホーム大阪大東店の地鎮祭について
アイフルホーム大阪大東店では、地鎮祭も大切な家づくりの一部と考え、お施主様に安心して参加いただけるよう、準備から当日のサポートまで丁寧にご案内しています。
お家づくりが初めての方がほとんどですので、初めての方でも流れがわかるよう、スタッフが式開始前に事前に説明を行い、当日は一緒に式を見守ります。
「やってよかった」と感じていただける、ご家族の思い出に残るあたたかい式となるようお手伝いさせていただきます。
地鎮祭の様子をSNSで発信中!
実際の地鎮祭の様子をSNSで投稿しています。
地鎮祭の様子を見てみたい方は、ぜひチェックしてみてください!