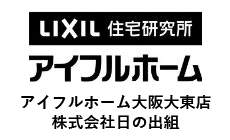子どもが成長するにつれ、家族のライフスタイルは変化します。さらに、年齢を重ねることで自分たちの体への負担や、高齢になった親との同居の可能性も出てきます。
そんな将来を考えたとき、「バリアフリー設計の家」は大きな安心をもたらします。
マイホームを検討している方に向けて、将来を見据えた住まい設計や、モデルハウスで体感できるバリアフリーの工夫を詳しく紹介します。

将来を見据えた住まいの設計ポイント
家づくりを考える時、どうしても「今の暮らしやすさ」に目が行きがちです。
しかし、家は何十年も住み続けるもの。10年後、20年後の家族構成や生活動線を想像することが大切です。
親との同居を見据えた間取り
「将来、親と一緒に暮らすかもしれない」という方は、1階に寝室を用意する間取りを検討しておきましょう。階段の昇り降りが必要ない生活は、高齢の親だけでなく、自分たちが年齢を重ねた時にも役立ちます。
可変性のある間取り
子どもが独立した後に部屋を仕切る・つなげるといったリフォームがしやすい間取りを選ぶことも重要です。将来のリフォームコストを抑えるために、あらかじめ可変性のある設計にしておくと良いでしょう。
メンテナンスへの配慮
長く暮らす住まいだからこそ、メンテナンスに配慮して素材や設備を選ぶと良いでしょう。床材は滑りにくく、傷がつきにくい素材を選ぶことで、転倒防止にもつながります。
手すりが必要になった時に後付けできるよう、扉や壁に下地補強しておくだけで、将来の負担を軽減することができます。
モデルハウスで体感できるバリアフリーの工夫
モデルハウスで必ずチェックしておきたい“バリアフリーの工夫”を紹介します。

段差をなくす
室内の段差は、つまずきや転倒の原因になりやすい箇所。
玄関・廊下・リビングなどの床の段差を極力なくす設計は、子どもや高齢者にとって安心です。
完全なフラットにできない場合は、段差を低くしてスロープを設ける方法もあります。

浴室に手すりを設置する
浴室は濡れていて滑りやすく、事故が起きやすい場所です。
手すりを設置することで、浴槽の出入りが安全になり、リスクを軽減することができます。

室内を引き戸にする
引き戸なら開閉がスムーズで通路の有効活用が可能です。
片手でも簡単に開閉できるため、子どもや高齢者にも優しい仕様です。
トイレの扉も引き戸にする
将来、介助が必要になった場合、トイレの扉は重要です。
引き戸にすることで、介助スペースを確保でき、安全性が高まります。
バリアフリーのご相談はモデルハウス見学会へ
「バリアフリーにしたいけど、実際どんな工夫ができるの?」という疑問を解決するには、モデルハウスを見て、体感するのが一番です。図面やカタログではイメージしづらい動線や段差、扉の開閉感も、実際に触れてみると納得感が違います。
さらに、モデルハウス見学会では、専門スタッフに相談できるチャンスがあります。
親と同居する場合の間取りの工夫、予算内でできるバリアフリーの範囲など具体的な相談をしながら、自分たちに合った家づくりを進めていきましょう。